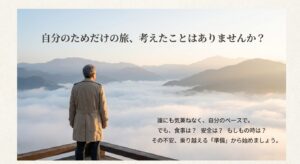「60代で仕事がない」は嘘?シニアの就労実態と働き方のコツ7選
定年を迎え、いざ仕事を探そうとしても「60代だと仕事がないのでは」と不安に感じていませんか。
年金生活への懸念や、社会とのつながりを持ち続けたいという思いから、多くの方がセカンドキャリアを模索しています。
この記事では、そうした不安を解消するため、60代の就労実態から具体的な仕事の探し方、働き方のコツまでを網羅的に解説。
実際に60歳を過ぎてもできる仕事は何か、逆にやめておいたほうがいい仕事はあるのかという疑問に答えるとともに、そもそも60歳以降働きたくない人の割合や、働かない人の割合のデータも交えて現状を明らかにします。
また、果たして60歳で正社員になれるのかという可能性、特に60代女性向けの求人の実情、そして年齢を重ねてミスばかりになったらどうしようという心配についても、具体的な対策を提案します。
ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の新たな一歩を踏み出すための参考にしてください。
- 60代のリアルな就労状況や働かない人の割合
- シニア歓迎の仕事の見つけ方と面接のコツ
- 経験を活かす働き方や再就職に有利な資格
- 年金受給と働き方のバランスに関する注意点
「60代仕事がない」は誤解?シニアの就労実態
- 60代で働かない人の割合はどのくらい?
- 60歳以降働きたくない人の本当の割合
- 60代女性向けの求人を見つける方法
- シニア歓迎の職場探し3つのポイント
- 60歳からでも正社員になれる可能性
60代で働かない人の割合はどのくらい?
結論から言うと、60代の多くの方は何らかの形で就業を継続しています。
パーソル総合研究所の調査によれば、正社員として20年以上勤務した人のうち、60歳から64歳で仕事をしていない人の割合は4.2%、65歳から69歳では10.7%という結果でした。
これは、多くの方が定年後も継続雇用や再就職を選んでいることを示しています。
もちろん、日本の人口のボリュームゾーンである60代が労働市場で重要な存在であることは間違いありません。
しかし、一部の方が就業継続を選ばない背景には、さまざまな理由が存在します。
このデータを踏まえると、「60代は全く仕事がない」というよりは、「働き方や条件が合わずに働かない選択をする人が一定数いる」と捉えるのがより正確な理解と言えるでしょう。
補足:シニアの就業率は年々増加傾向
総務省のデータによると、シニア世代の就業率は年々増加しています。
2021年の「高年齢者雇用安定法」の改正により、企業には70歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられ、60代が活躍できる環境は社会全体で整備されつつある状況です。
60歳以降働きたくない人の本当の割合
現在働いていない60代の方々が、なぜその選択をしたのか、その理由を見ていきましょう。
最も多い理由は「もう働きたくない」というもので、60歳から64歳で50.0%、65歳から69歳では58.4%に上ります。
長年のキャリアで心身ともに疲労を感じたり、経済的に安定して働き続ける必要性を感じなくなったりすることが主な要因と考えられます。
しかし、注目すべきは他の理由です。
「やりたい仕事が見つからない」
「就業日・時間の条件が合わない」
「キャリアやスキルが活かせない」といった、
仕事と自身の希望とのミスマッチを理由に挙げる人が、60代前半で38.5%、後半で41.6%もいるのです。
これは、働きたい意欲はあっても、適切な仕事が見つからないために、やむを得ず「働かない」という選択をしている方が少なくない現実を示唆しています。
注意点:働きたい意欲とのギャップ
これらのデータから、働かない60代の中には「働きたくない層」と「働きたいが条件が合わない層」の二つが存在することがわかります。
もしあなたが後者であれば、仕事探しの方法や視野を少し変えることで、活躍の場を見つけられる可能性は十分にあります。
60代女性向けの求人を見つける方法

60代の女性が活躍できる仕事は数多く存在し、探し方にはいくつかのコツがあります。
まず、ハローワークの「生涯現役支援窓口」や、シルバー人材センターといった公的機関を活用する方法が挙げられます。
これらの機関はシニアの就職支援に特化しており、専門の相談員からアドバイスを受けられる点が魅力です。
また、民間の求人サイトを利用するのも非常に有効な手段といえるでしょう。
その際は、「しゅふJOB」や「マイナビミドルシニア」のように、主婦やシニア層に特化したサイトを選ぶのがおすすめです。
一般的な求人サイトよりも、短時間勤務や未経験者歓迎の求人が見つかりやすくなっています。
具体的な検索のコツ
求人サイトで検索する際は、「60代活躍中」「シニア応援」「未経験歓迎」といったキーワードで絞り込むと、効率的に仕事を探せます。
特に、子育てや介護の経験といった、これまでの人生経験を強みとしてアピールできる職種(家事代行、マンション管理員、介護補助など)は、採用の可能性が高まる傾向にあります。
私も求人サイトを見る際は、まず「60代活躍中」で絞り込みます。
同世代の方がすでに働いている職場だと思うと、安心して応募できますよね。
焦らず、ご自身のペースに合った探し方を見つけることが大切です。
シニア歓迎の職場探し3つのポイント
「シニア歓迎」と記載されている求人の中から、自分に合った職場を見つけるためには、以下の3つのポイントを意識することが重要です。
1. 身体を動かす仕事かどうか
リクルートワークス研究所の調査によると、65歳以上の方は「身体を動かす仕事に価値を感じる」傾向が強いことがわかっています。
適度に体を動かす仕事は、健康維持にもつながる大きなメリットがあります。
マンションの管理や清掃、スーパーの品出しなどは、体への負担が少なく、長く続けやすい仕事の代表例です。
ただし、過度な力仕事は避けるべきなので、応募前に仕事内容をしっかり確認しましょう。
2. やりがいや貢献を実感できるか
定年前と比較して、「他者への貢献」に価値を見出すシニアは多くなります。
介護職や家事代行スタッフのように、直接「ありがとう」と言われる機会が多い仕事は、大きなやりがいにつながるでしょう。
自分の仕事が誰かの役に立っていると実感できるかどうかは、長く働き続けるための重要なモチベーションになります。
3. 同世代の仲間がいるか
すかいらーくグループやモスバーガー、マクドナルドといった大手企業は、シニア世代の採用を積極的に行っています。
このような職場では、同世代の仲間と出会いやすく、互いに支え合いながら働けるというメリットがあります。
価値観が近い仲間がいることで、職場でのストレスが軽減され、仕事に行くのが楽しみになることも少なくありません。
60歳からでも正社員になれる可能性

結論として、60歳から未経験の職種で正社員になるのは簡単ではありませんが、不可能ではありません。
特に、これまでのキャリアで培った専門スキルや管理職経験を活かせる場合は、即戦力として採用される可能性があります。
最も現実的なのは、現在勤務している会社の「継続雇用制度(再雇用制度や勤務延長制度)」を利用することです。
高年齢者雇用安定法により、企業は希望者に対して65歳までの雇用確保措置を講じることが義務付けられており、慣れた環境で働き続けられる安心感があります。
もし転職を考えるのであれば、人材不足が深刻な業界を狙うのが一つの戦略です。
例えば、介護業界や警備業界、ドライバーなどは、年齢に関わらず正社員の求人が比較的多く見られます。
また、経理や人事といった管理部門の専門職も、経験者であれば転職のチャンスがあります。
正社員にこだわらず、契約社員や嘱託社員といった雇用形態も視野に入れると、選択肢はさらに広がるでしょう。
正社員を目指すなら
ハイクラス向けの転職エージェントに登録し、これまでの経験を棚卸ししてみることをお勧めします。
自分では気づかなかった強みを発見し、思わぬ企業から声がかかる可能性もあります。
「60代で仕事がない」を乗り越える働き方のコツ
- 60歳を過ぎてもできる仕事の具体例
- やめておいたほうがいい仕事の特徴とは
- 仕事でミスばかりと悩んだ時の対処法
- 経験を活かせる仕事とスキルの学び直し
- 年金をもらいながら働く際の注意点
- 60代からでも取得できる再就職に有利な資格
- 面接で評価される経験の伝え方と注意点
60歳を過ぎてもできる仕事の具体例
60歳を過ぎてからでも活躍できる仕事は、多岐にわたります。
ここでは、特に求人が多く、未経験からでも始めやすい職種をいくつか紹介します。
| 職種 | 仕事内容の例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 介護・福祉系 | 食事の準備、利用者の補助、送迎など | 人生経験が活かせる。人手不足のため求人が豊富。 |
| 清掃・管理系 | オフィスビルやマンションの清掃、施設の管理 | 自分のペースで働ける。早朝などの短時間勤務が多い。 |
| 警備員 | 施設警備、交通誘導、イベント警備など | 未経験者向けの研修が充実。健康であれば長く続けられる。 |
| ドライバー | タクシー、軽貨物配送、送迎バスなど | 運転が好きな人向け。普通免許で始められる仕事も多い。 |
| 事務・軽作業 | データ入力、伝票整理、倉庫でのピッキング | 体力的な負担が少ない。PCの基本操作ができると有利。 |
| サービス業 | 飲食店のホール、家事代行、セレモニースタッフ | コミュニケーション能力が活かせる。感謝される機会が多い。 |
これらの仕事は、特別なスキルがなくても始められるものがほとんどです。
まずはアルバイトやパートから始めて、仕事に慣れていくという方法も良いでしょう。
やめておいたほうがいい仕事の特徴とは
長く健康的に働き続けるためには、避けるべき仕事の特徴を知っておくことも大切です。
すべての人が当てはまるわけではありませんが、一般的に以下の3つの特徴を持つ仕事は慎重に検討することをおすすめします。
1. 体力的な負担が極端に大きい仕事
若い頃と同じような感覚で、重量物を頻繁に運ぶ仕事や、長時間の立ち仕事を選ぶと、足腰を痛める原因になりかねません。
特に、夜勤が中心となる仕事は生活リズムが乱れやすく、体調を崩すリスクが高まります。
2. 変化のスピードが速すぎるIT関連の仕事
新しい技術やツールが次々と登場する業界は、常に学び続ける意欲が求められます。
もちろん、デジタルスキルを身につけることは素晴らしいことですが、最先端の技術を追い続ける必要がある職種は、精神的なストレスが大きくなる可能性があります。
3. 個人の裁量がほとんどない単純作業
やりがいを求める方にとって、誰にでもできる単純作業の繰り返しは、モチベーションの低下につながることがあります。
これまでの経験が全く活かせず、工夫の余地がない仕事は、働く目的が収入だけでない場合には、物足りなさを感じるかもしれません。
仕事でミスばかりと悩んだ時の対処法
年齢を重ねると、記憶力や集中力の低下を感じ、「以前はしなかったようなミスをしてしまう」と悩む方も少なくありません。
しかし、それは自然な変化であり、過度に自分を責める必要はないのです。
大切なのは、ミスを前提とした上で、それを防ぐ工夫をすることです。
まず、忘れないようにメモを取ることを徹底しましょう。
スマートフォンのメモ機能や小さな手帳を活用し、指示されたことややるべきことをすぐに記録する習慣をつけることが有効です。
そのメモをどこに置いたか忘れないよう、常に同じ場所に置くルールを決めておくのも良い方法です。
複数の業務が重なって混乱しそうな時は、一人で抱え込まず、正直に周囲に助けを求めることも重要です。
「今、少し立て込んでいまして」と伝えるだけで、周りの同僚がサポートしてくれることもあります。
年齢を重ねたからこそ、素直に助けを求められる謙虚さも大切なスキルの一つと言えるでしょう。
いくら頑張っても、脳の老化を完全に止めることはできません。
くよくよせずに、できる対策を一つずつ試していく姿勢が大切です。
経験を活かせる仕事とスキルの学び直し
60代の最大の強みは、長年の社会人生活で培ってきた豊富な経験と知識です。
特別な資格がなくても、マネジメント経験や顧客対応のスキル、特定の業界知識などは、大きなアピールポイントになります。
特に、人材不足に悩む中小企業では、若手の育成や業務改善を担えるベテラン人材を求めているケースが少なくありません。
一方で、現代の職場では基本的なPCスキルが求められる場面が増えています。
もし、PC操作に不安がある場合は、「リスキリング(学び直し)」に挑戦してみるのがおすすめです。
何も専門的なプログラミングを学ぶ必要はありません。
WordやExcelの基本操作、メールのやり取り、オンライン会議ツールの使い方などを習得するだけでも、応募できる仕事の幅は格段に広がります。
学び直しには公的支援を活用
ハローワークが実施している「職業訓練(ハロートレーニング)」では、PCスキルや簿記、介護など、就職に役立つさまざまなコースを無料で受講できます(テキスト代などは自己負担)。
こうした制度をうまく活用し、自信を持って新たなキャリアに挑戦しましょう。
年金をもらいながら働く際の注意点

60代で働く場合、多くの方が年金を受給しながら収入を得ることになります。
このとき、注意したいのが「在職老齢年金制度」です。
これは、働きながら受け取る給与(正確には総報酬月額相当額)と年金(基本月額)の合計額に応じて、年金の一部または全額が支給停止される仕組みを指します。
具体的には、65歳以上の方の場合、給与と年金の合計額が月額50万円(令和6年度)を超えると、超えた額の半分の年金が支給停止となります。
以前は47万円でしたが、令和6年度から基準額が引き上げられました。この基準額は毎年改定される可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。
働き損にならないために
フルタイムでしっかり働きたいと考えている方は、自身の給与と年金額を把握し、支給停止額がいくらになるか事前にシミュレーションしておくことをお勧めします。
働き方を調整することで、手取り収入が減ってしまう「働き損」を避けることができます。
詳細は、日本年金機構の公式サイトや、お近くの年金事務所で確認してください。
(参照:日本年金機構)
60代からでも取得できる再就職に有利な資格
資格は、再就職を目指す上で大きな武器になります。
60代からでも挑戦しやすく、かつ実務に直結しやすいおすすめの資格をいくつか紹介します。
1. 介護職員初任者研修
高齢化社会において需要が絶えない介護業界の入門資格です。
比較的短期間で取得でき、全国どこでも求人が豊富なため、安定して長く働きたい方におすすめ。
自身の介護経験を活かすこともできます。
2. 宅地建物取引士(宅建)
不動産業界で必須となる国家資格。
不動産の売買や賃貸の仲介で重要事項の説明といった独占業務を行えます。
年齢に関係なく求人があり、パートタイムでの勤務も可能な場合が多いです。
3. ファイナンシャル・プランナー(FP)
金融や保険、不動産に関する知識を証明する資格です。
自身のライフプランニングにも役立つ上、金融機関や保険代理店での仕事に活かせます。
同世代のお客様に寄り添ったアドバイスができる強みがあります。
4. マンション管理士・管理業務主任者
マンションの管理組合へのアドバイスや、管理会社の重要事項説明などを行うための国家資格です。
定年退職した方が多く活躍しており、セカンドキャリアの定番資格の一つとなっています。
面接で評価される経験の伝え方と注意点

60代の就職面接では、これまでの豊富な経験を効果的にアピールすることが合否を分けます。
単に職歴を羅列するのではなく、「その経験を通じて、入社後にどう貢献できるか」を具体的に伝えることが重要です。
例えば、「長年、営業として培った傾聴力で、お客様との信頼関係を築きます」「管理職として若手を指導した経験を、新人の育成に活かせます」といった形で、応募先の業務内容と結びつけて話しましょう。
一方で、注意すべき点もあります。
過去の実績や役職に固執し、横柄な態度に見られないように気をつけてください。
面接官が年下であっても、謙虚な姿勢と敬意を忘れないことが大切です。
「教えてもらう」という柔軟な姿勢を示すことで、新しい環境にもすぐ適応できる人材だと評価されます。
服装は清潔感が第一です。
必ずしもスーツである必要はありませんが、襟付きのシャツやジャケットを着用するなど、場にふさわしいきちんとした身だしなみを心がけましょう。
第一印象が、あなたの経験に説得力を持たせることにつながります。
60代仕事がないと悩む前に試すこと
- 60代の就業率は年々増加しており活躍の場は広がっている
- 働かない理由には意欲低下だけでなく希望とのミスマッチも多い
- ハローワークやシニア向け求人サイトを積極的に活用する
- 女性は人生経験を活かせる家事代行や介護補助も視野に入れる
- シニア歓迎の職場はやりがいや健康維持につながりやすい
- 正社員を目指すなら継続雇用や人手不足の業界を検討する
- 介護・清掃・警備など未経験から始められる仕事は多数ある
- 体力的に過酷な仕事や変化が速すぎる業界は慎重に判断する
- ミスを恐れずメモや周囲への相談で工夫することが大切
- 長年の経験は最大の武器であり貢献できることを伝える
- PCスキルなど学び直しにはハロートレーニングが有効
- 年金と給与の合計が一定額を超えると年金が減る制度に注意
- 再就職に有利な資格取得も有効な選択肢の一つ
- 面接では過去の実績より未来の貢献と謙虚な姿勢をアピール
- まずはパートから始めて新しい環境に慣れるのも良い方法
関連記事
「60代になって『仕事が覚えられない』と感じる原因と解決策を解説」
「60代で友達いないを解決する方法と人付き合いの始め方」