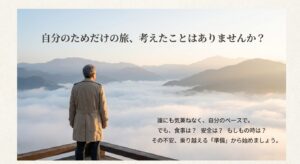60代の一人暮らしを豊かにする住まいとお金のリアルな話
60代を迎え、定年退職や子どもの独立、あるいは離婚といった人生の節目を機に、一人暮らしを始める方は少なくありません。
私自身も60代で一人暮らしを満喫している一人ですが、この生活を始めるにあたり、様々な期待と同時に不安があったことを今でも覚えています。
特に、男性も女性も共通して直面するのが、住まいと経済的な問題ではないでしょうか。
今後の人生を過ごす大切な部屋探しでは、物件をどう選ぶか、どのような間取りが良いのか悩みます。
また、年金生活が現実味を帯びる中で、貧困に陥らないか、日々の食費をどう管理すればよいのかという心配は尽きません。
しかし、ご安心ください。
しっかりとした準備と少しの工夫で、60代の一人暮らしは、誰にも気兼ねすることのない自由で豊かな時間へと変えることができます。
この記事では、そんな充実したセカンドライフを送るための、具体的な楽しみ方やヒントを私の経験も交えながら詳しく解説していきます。
- 60代の一人暮らしに適した住まいの探し方
- 老後の経済的な不安を解消する具体的な資金計画
- 男性・女性それぞれの視点から見た豊かな暮らしのヒント
- 健康を維持し社会と繋がり続けるための方法
60代の一人暮らしで考える住まいと経済状況

- 離婚後に必要な生活の備え
- 60代が賃貸物件を探す際の注意点
- 快適な暮らしを実現する部屋の選び方
- 目的別におすすめの間取りを紹介
- 貧困に陥らないための資金計画
- 無理なく食費を管理するコツ
離婚後に必要な生活の備え

60代での離婚は、精神的な負担だけでなく、その後の生活基盤をどう再構築するかという現実的な課題に直面します。
特に長年連れ添った後の「熟年離婚」では、生活スタイルが大きく変わるため、事前の準備が何よりも重要になります。
まず考えるべきは、財産分与と年金分割です。
これらは離婚後の生活を支える上で極めて重要な要素です。婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産(預貯金、不動産、保険など)は、貢献度に応じて公平に分配される権利があります。
また、厚生年金に加入していた期間がある場合は、年金分割の請求を忘れてはいけません。
将来受け取る年金額に大きく影響するため、必ず専門家に相談し、ご自身の権利を正しく主張しましょう。
離婚後の生活で準備すべきこと
- 財産の把握:
夫婦の共有財産をリストアップし、正確な価値を把握する。 - 年金分割の確認
「ねんきん定期便」などで情報を確認し、分割の割合を話し合う。 - 当面の生活費確保
財産分与が完了するまでの生活費を計算し、確保しておく。 - 住まいの確保
新たな住居を探すか、現在の住居に住み続けるかを決める。
次に重要なのが、継続的な収入源の確保です。
専業主婦(主夫)だった方やパート勤務だった方は、年金や財産分与だけでは生活が苦しくなる可能性があります。
60代からの再就職は簡単ではありませんが、シルバー人材センターの活用や、これまでの経験を活かせる短期の仕事など、選択肢はゼロではありません。
まずは無理のない範囲で働ける場所を探し、社会とのつながりを保ちながら収入を得る道筋を立てることが、精神的な安定にも繋がります。
60代が賃貸物件を探す際の注意点

さて、いざ一人暮らしを始めようと賃貸物件を探し始めると、60代という年齢が思わぬ壁になることがあります。
残念ながら、家主側には「収入面の不安(年金生活)」「健康面の不安(孤独死のリスク)」といった懸念があり、若い世代と比べて入居審査が厳しくなる傾向があるのは事実です。
私も部屋探しを始めた当初は、いくつかの物件で良い返事がもらえず、少し落ち込んだ経験があります。
しかし、ポイントを押さえて準備すれば、必ずご自身に合った良い部屋は見つかりますので、諦めないでくださいね。
入居審査をスムーズに進めるためには、家主の不安を払拭する材料をこちらから提示することが効果的です。
具体的には、以下のような点が挙げられます。
高齢者の入居審査で注意すべき点
連帯保証人の確保が難しいという問題は多くの方が直面します。
兄弟や子どもに頼めない場合、審査で不利になることがあります。
また、年金収入だけでは家賃の支払い能力を懸念されるケースも少なくありません。
審査通過のための具体的な対策
これらの不安を解消するため、家賃債務保証会社の利用は今や必須と言えるでしょう。
費用はかかりますが、家賃滞納のリスクを保証してくれるため、家主の信頼を得やすくなります。
最近では、保証会社の利用を必須とする物件がほとんどです。
また、子どもや親族が近くに住んでいる場合は、そのことをアピールするのも有効です。
緊急連絡先としてだけでなく、何かあった時にすぐに駆けつけてくれる存在がいることは、家主にとって大きな安心材料となります。
預貯金が十分にある場合は、残高証明書を提示して支払い能力を示すのも良い方法です。
さらに、UR賃貸住宅(旧公団住宅)や「高齢者向け優良賃貸住宅」といった公的な物件も視野に入れることをおすすめします。
これらの物件は礼金や仲介手数料、更新料が不要な場合が多く、保証人も原則不要です。
高齢者の入居を前提としているため、審査のハードルが低いだけでなく、バリアフリー設計になっているなど、安心して暮らせる環境が整っています。
私もUR賃貸住宅に住んでいますが、設備が少し古い部分はありますが、それ以外で気になることはありません。
また同じような高齢者が多いため、ある意味安心して過ごせています。
階段などで住民とすれ違えば、挨拶するなどコミュニケーションが簡単に取れるのもメリットだと感じています。
気軽に他人と話せる環境なので、孤独感や孤立感をある程度解消できるのもメリットです。
快適な暮らしを実現する部屋の選び方

無事に審査の目処が立ったら、次はどのような部屋を選ぶかです。
60代からの部屋選びは、若い頃とは少し視点を変える必要があります。
「今」の元気な自分だけでなく、「10年後、20年後の自分」を想像して選ぶことが、長く快適に暮らすための秘訣です。
利便性:徒歩圏内の環境を重視する
まず最優先したいのが、利便性の高さです。
車の運転が難しくなる可能性も考え、スーパーやドラッグストア、郵便局、そして何よりかかりつけの病院やクリニックが徒歩圏内にある立地を選びましょう。
日々の買い物が楽なだけでなく、体調が優れない時でもすぐに医療機関にかかれる安心感は、何物にも代えがたいものです。
また、バス停や駅が近いことも重要です。
友人との集まりや趣味の活動に出かける際、公共交通機関へのアクセスが良いと、行動範囲がぐっと広がります。
安全性:バリアフリーと防犯対策
次に重要なのが安全性です。
室内のわずかな段差での転倒が、大きな怪我につながる可能性があります。
できるだけ室内に段差がないバリアフリー仕様の物件が理想的です。
特に、浴室やトイレに手すりが設置されているか、通路幅が十分に確保されているかなどを内見時にしっかり確認しましょう。
建物の階数については、エレベーターがある物件を選ぶのが大前提です。
その上で、災害時にエレベーターが停止することも想定し、階段での移動が比較的容易な2階や3階などの低層階を選ぶと、いざという時に安心です。
防犯面では、オートロックやモニター付きインターホンが設置されている物件を選ぶことで、不審者の侵入を防ぎ、安心して暮らすことができます。
管理人さんが常駐しているマンションであれば、さらに心強いでしょう。
内見時のチェックポイント
- 日当たりと風通しは良いか(心身の健康に影響します)
- 収納スペースは十分にあるか
- コンセントの位置と数は使いやすいか
- 近隣の騒音や住民の雰囲気はどうか
目的別におすすめの間取りを紹介
一人暮らしと一言でいっても、そのライフスタイルは人それぞれです。
ここでは、いくつかのタイプ別に、おすすめの間取りとそのメリット・デメリットをまとめてみました。
ちなみに私は1LDKに住んでいます。
寝室と生活空間をきっちり分けられるので、生活にメリハリがついて気に入っていますよ。
ご自身の暮らし方をイメージしながら、最適な間取りを見つけてみてください。
| 間取りタイプ | おすすめのライフスタイル | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 1K / ワンルーム | ・荷物が少なくシンプルに暮らしたい ・家賃を最大限に抑えたい ・掃除の手間を減らしたい |
・家賃が安く経済的 ・掃除が楽で管理しやすい ・光熱費を抑えられる |
・収納が少ない ・来客時にプライベート空間がない ・料理の匂いが部屋に広がりやすい |
| 1DK / 1LDK | ・寝食の空間を分けたい ・友人を招くことがある ・趣味のスペースが欲しい |
・生活にメリハリがつく ・来客用のスペースを確保できる ・収納が比較的多い |
・1Kに比べて家賃や光熱費が高くなる ・部屋数が増える分、掃除の手間が増える |
| 2K / 2DK | ・在宅で仕事をする ・独立した趣味の部屋が欲しい ・将来、家族が泊まりに来る可能性がある |
・仕事部屋や趣味部屋を確保できる ・収納力が非常に高い ・生活空間にゆとりが生まれる |
・家賃がさらに高くなる ・使わない部屋が出てくる可能性がある ・一人では広く感じ、管理が大変になることも |
重要なのは、広すぎないことです。
部屋数が多いと掃除や管理が負担になりますし、使わない部屋は物置になりがちです。
ご自身の体力や生活スタイルを客観的に見極め、無理なく管理できる広さの住まいを選ぶことが、快適な一人暮らしの第一歩です。
貧困に陥らないための資金計画
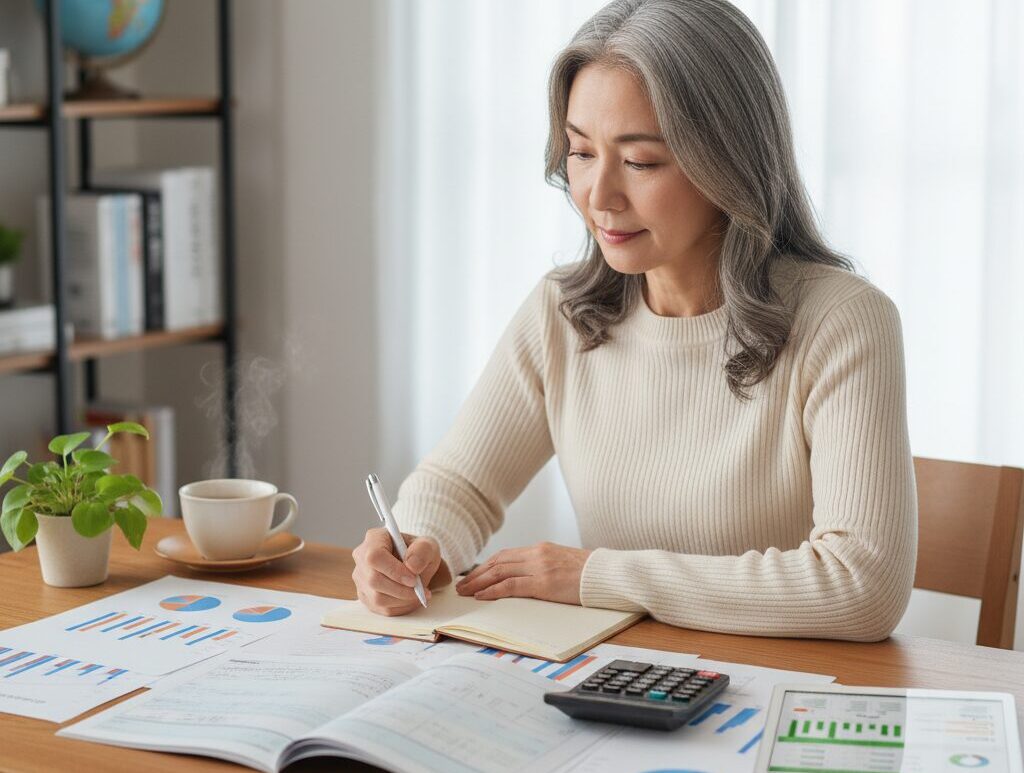
住まいの目処が立ったら、次はいよいよお金の話です。
60代の一人暮らしで最も大きな不安は、やはり経済的な問題でしょう。
「年金だけで暮らしていけるだろうか」「病気になったらどうしよう」といった心配は、誰もが抱えるものです。
しかし、事前に現状を把握し、しっかりと計画を立てることで、漠然とした不安を解消することができます。
まずは、ご自身の「収入」と「支出」を正確に把握することから始めましょう。
収入を把握する
主な収入源となるのは公的年金です。
毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」や、日本年金機構の「ねんきんネット」で、将来受け取れる年金額の概算を確認できます。
これに加えて、個人年金や企業年金、パートなどの労働収入があれば、それらも合算して月々の総収入を算出します。
支出を把握する
次に、1ヶ月にどれくらいの支出があるかを洗い出します。
家計簿アプリなどを活用すると便利です。
主な支出項目
- 固定費:家賃、水道光熱費、通信費、保険料など
- 変動費:食費、日用品費、交通費、医療費、交際費、趣味・娯楽費など
総務省の家計調査(2023年)によると、65歳以上の単身無職世帯の消費支出は月平均で約14.3万円というデータがあります。
これはあくまで平均値ですが、ご自身の支出と比較してみることで、使いすぎている項目がないかを見直すきっかけになります。
(参照:総務省統計局 家計調査報告)
収入から支出を差し引いて、毎月赤字になっていないかを確認します。
もし赤字になるようであれば、支出の見直しや、収入を増やす方法を考えなければなりません。
例えば、格安スマホへの乗り換えで通信費を削減したり、働く日数を少し増やしたりといった対策が考えられます。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)などを活用し、将来のために少しでも資産を増やす準備をしておくことも、心の余裕につながります。
無理なく食費を管理するコツ
日々の支出の中で、工夫次第で大きく節約できるのが食費です。
一人暮らしは外食やコンビニ弁当に頼りがちになりますが、それでは栄養が偏り、出費もかさんでしまいます。
健康維持と節約のためにも、できるだけ自炊を心がけるのがおすすめです。
私も現役時代は料理などほとんどしませんでしたが、やってみると意外と楽しいものですよ。
自分で作った料理は美味しいですし、何より安上がりです。
今日は何を作ろうかと考えるのが、日々のちょっとした楽しみになっています。
無理なく食費を管理するための、いくつかの簡単なコツをご紹介します。
買い物は週に1〜2回にまとめる
毎日スーパーに行くと、つい不要なものまで買ってしまいがちです。
1週間分の大まかな献立を考え、買い物リストを作ってから出かけることで、無駄買いを防ぐことができます。
特売日などを狙ってまとめ買いするのも良いでしょう。
下ごしらえ・作り置きを活用する
時間がある時に、野菜を切っておいたり、数日分の常備菜を作っておいたりすると、毎日の調理がぐっと楽になります。
ご飯も多めに炊いて一食分ずつ冷凍しておけば、いつでも手軽に食べられます。
簡単な節約&健康レシピのヒント
旬の野菜は安くて栄養価も高いので、積極的に取り入れましょう。
また、豆腐や納豆、卵、鶏むね肉といった安価で高タンパクな食材もおすすめです。
具沢山の味噌汁やスープは、一杯で満足感が得られ、野菜もたくさん摂れるので一石二鳥です。
一人暮らしだと食材を余らせてしまうこともありますが、冷凍保存をうまく活用すれば、食品ロスを減らしながら節約につなげることができます。
無理のない範囲で、楽しみながら自炊に取り組んでみてください。
豊かな60代一人暮らしを送るためのヒント

- 60代男性が注意すべきポイント
- 60代女性が意識したい暮らし方
- 新しい生きがいを見つける楽しみ方
- 健康リスクと利用できる支援制度
- 地域コミュニティへの具体的な参加方法
60代男性が注意すべきポイント
男性の一人暮らし、特にこれまで家事を奥様に任せきりだったという方は、慣れない生活に戸惑うことも多いかもしれません。
自由を満喫できる一方で、意識しておかないと思わぬリスクに直面することもあります。
ここでは、男性が特に注意すべき3つのポイントを挙げます。
健康管理と食生活の乱れ
最大の課題は健康管理です。
定年退職後は通勤などで体を動かす機会が激減し、運動不足になりがちです。
また、食事が面倒になり、インスタント食品やコンビニ弁当ばかりで済ませてしまうと、栄養バランスが崩れ、生活習慣病のリスクが高まります。
意識的にウォーキングなどの軽い運動を取り入れ、前述したような簡単な自炊に挑戦するなど、健康的な生活習慣を自分で作る意識が大切です。
社会的孤立
現役時代は会社というコミュニティに属していましたが、退職後は人との繋がりが希薄になりがちです。
特に男性は、近所付き合いや地域の活動に積極的に参加するのが苦手な方も多いのではないでしょうか。
しかし、孤立は心身の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、孤独死のリスクにも直結します。
勇気を出して、地域のサークルやボランティアに参加してみることを強くおすすめします。
家事スキル
掃除、洗濯、料理といった基本的な家事スキルは、快適な生活を送る上で不可欠です。
これまでやってこなかった方も、今から少しずつ覚えれば問題ありません。
最近はインターネットで簡単なレシピや掃除のコツをすぐ調べられます。
身の回りを清潔に保つことは、精神的な衛生を保つ上でも非常に重要です。
60代男性の孤独死は、他の年代・性別に比べて突出して多いというデータがあります。
これは決して他人事ではありません。「自分は大丈夫」と思わず、意識的に人との関わりを持ち、自身の健康状態に気を配ることが何よりも重要です。
60代女性が意識したい暮らし方
一方、女性の場合は、男性とはまた違った視点での備えや心構えが大切になります。
家事やご近所付き合いに慣れている方が多い一方で、特に注意したい点もあります。
経済的な自立と情報収集
女性は男性に比べて平均寿命が長い分、老後資金がより多く必要になる傾向があります。
また、現役時代の収入格差から、受け取れる年金額が少ないケースも少なくありません。
前述の資金計画をしっかりと立て、経済的に自立できる基盤を築くことが大切です。
公的な支援制度や自治体のサービスなど、利用できるものは積極的に活用するために、日頃から情報収集を怠らないようにしましょう。
防犯意識を高く持つ
高齢の女性の一人暮らしは、残念ながら犯罪のターゲットにされやすいという現実があります。
「自分だけは大丈夫」という過信は禁物です。
モニター付きインターホンで相手を確認してからドアを開ける、見知らぬ訪問者には安易に対応しない、戸締りを徹底するなど、基本的な防犯対策を習慣づけましょう。
少しでも不安を感じたら、すぐに警察や家族に相談することが大切です。
心身の健康と友人関係
女性は男性よりも地域のコミュニティに溶け込みやすい傾向がありますが、それでも親しい友人との繋がりは意識して育む必要があります。
何でも話せる友人がいることは、日々の楽しみになるだけでなく、精神的な支えにもなります。
ランチや日帰り旅行など、定期的に会う機会を作ることで、孤独感を防ぎ、心身の健康を保つことにつながります。
私の周りでも、女性の方々は趣味のサークルや習い事で活発に交流を楽しんでいますね。
そうした繋がりが、日々の生活に彩りと安心感をもたらしているようです。
新しい生きがいを見つける楽しみ方

一人暮らしの最大の魅力は、なんといっても「自由な時間」です。
誰にも気兼ねすることなく、自分の好きなことに時間を使えるこの特権を、楽しまない手はありません。
現役時代は忙しくてできなかったことに、どんどん挑戦してみましょう。
「何をしたらいいかわからない」という方は、以下を参考にしてみてはいかがでしょうか。
一人時間を豊かにする活動例
- 趣味に没頭する
読書、映画鑑賞、ガーデニング、釣り、写真、陶芸など、興味のあったことを深掘りしてみる。 - 新しいことを学ぶ
パソコン教室、英会話、料理教室、地域の大学の公開講座などに通ってみる。
新しい知識は人生を豊かにします。 - 体を動かす
ウォーキング、ヨガ、ジム、水泳、ダンスなど。
健康維持と仲間作りの一石二鳥です。 - 旅行に出かける
平日の空いている時期を狙って、温泉地でのんびりしたり、歴史的な街並みを散策したり。
一人旅も気ままで良いものです。 - セカンドキャリアに挑戦
短時間でも仕事を続けることで、社会との繋がりや収入を得られます。
経験を活かした仕事も良いでしょう。
大切なのは、少しでも興味が湧いたら、まずは一歩踏み出してみることをオススメします。
最初から完璧を目指す必要はありません。合わなければ、また別のことを探せば良いのです。
様々なことに挑戦する中で、きっと夢中になれる「生きがい」が見つかるはずです。
健康リスクと利用できる支援制度
楽しく豊かな一人暮らしを送る上で、土台となるのが健康です。
しかし、年齢を重ねると、自分では予期せぬ体調の変化や怪我のリスクは高まります。
「もし家で倒れたら」「急に具合が悪くなったら」といった不安は、一人暮らしの大きな課題です。
こうした健康リスクに備えるためには、日頃の健康管理はもちろんのこと、いざという時に助けを求められる仕組みを整えておくことが非常に重要です。
安否確認・見守りサービスの活用
近年、高齢者の一人暮らしをサポートする様々な民間サービスが登場しています。
例えば、以下のようなものがあります。
- センサー型
ポットや冷蔵庫の使用状況、室内の人の動きをセンサーが感知し、一定時間動きがない場合に家族や警備会社に自動で通報するサービス。 - 通報型
緊急時にペンダント型のボタンを押すだけで、警備会社が駆けつけてくれるサービス。 - 訪問・電話型
スタッフが定期的に自宅を訪問したり、電話をかけたりして安否を確認するサービス。
これらのサービスは費用がかかりますが、万が一の際の安心感は絶大です。
ご自身の状況や予算に合わせて検討してみる価値は十分にあります。
公的な相談窓口と支援制度
費用をかけずに利用できる公的な支援もたくさんあります。
どこに相談すれば良いか分からない場合は、まずお住まいの地域にある「地域包括支援センター」に連絡してみましょう。
ここは、高齢者の暮らしに関する総合相談窓口で、保健師や社会福祉士などの専門家が、健康、福祉、介護など、様々な悩みに対して無料で相談に乗ってくれます。
(参照:厚生労働省 地域包括支援センター)
他にも、低所得の高齢者などが住宅の確保で困らないように支援する「住宅セーフティネット制度」や、自治体によっては独自の高齢者支援サービス(配食サービス、緊急通報システムの設置補助など)を実施している場合があります。
お住まいの市区町村の役所のウェブサイトなどで確認してみましょう。
地域コミュニティへの具体的な参加方法

前述の通り、社会的孤立は心身の健康を損なう大きなリスクです。
健康で豊かな一人暮らしを続けるためには、意識的に外に出て、人と交流する機会を作ることが欠かせません。
「今さら新しい人間関係なんて面倒だ」と思われる気持ちも分かります。
ですが、利害関係のないフラットな繋がりは、現役時代の人間関係とはまた違った心地よさがありますよ。
地域のコミュニティに参加するための入り口は、意外とたくさんあります。
地域の活動に参加する
- 自治会・町内会
地域の清掃活動やイベントなどに顔を出すだけでも、ご近所さんと顔見知りになる良いきっかけになります。 - 趣味のサークル
地域の広報誌や公民館の掲示板には、囲碁、将棋、カラオケ、手芸、ダンスなど、様々なサークルのメンバー募集情報が掲載されています。
共通の趣味があれば、自然と会話も弾みます。 - 公民館・文化センターの講座
比較的安価な料金で、様々な講座が開かれています。新しいことを学びながら、仲間作りもできます。
社会貢献活動に参加する
- シルバー人材センター
働くことを通じて、社会との繋がりを維持できます。
地域の企業や家庭から請け負った軽作業などが中心で、無理のない範囲で働けます。 - ボランティア活動
地域の美化活動、学童の見守り、高齢者施設での傾聴ボランティアなど、多種多様な活動があります。
人の役に立つ喜びは、大きな生きがいになります。
大切なのは、完璧を求めず、まずは気軽に参加してみることです。「ちょっと顔を出してみる」くらいの気持ちで、興味のある場所に足を運んでみてはいかがでしょうか。
豊かな60代一人暮らしの総まとめ
この記事では、60代から始める一人暮らしを、より豊かで安心なものにするための様々なヒントをご紹介しました。
最後に、大切なポイントをリストで振り返ってみましょう。
- 60代の一人暮らしは準備次第で自由で豊かな時間になる
- 離婚時は財産分与や年金分割を専門家と相談することが重要
- 賃貸物件は保証会社の利用や公的住宅の検討が有効
- 部屋選びは将来を見据え利害性と安全性を最優先する
- 間取りは広すぎず自分の生活スタイルに合ったものを選ぶ
- まず収入と支出を正確に把握し資金計画を立てることが基本
- 年金や貯蓄で不足する場合は働くことも選択肢に入れる
- 食費の節約と健康維持のため無理のない範囲で自炊を心がける
- 男性は特に健康管理と社会的孤立に注意が必要
- 女性は防犯意識と経済的な自立を常に意識する
- 自由な時間を活かして新しい趣味や学びに挑戦する
- 緊急時に備え安否確認サービスや公的支援の情報を集めておく
- 孤立を防ぐため地域コミュニティへ積極的に参加する
- 完璧を目指さずまずは気軽な気持ちで一歩踏み出すことが大切
- 60代からの一人暮らしは人生の新しいステージの始まり
関連記事
「60代の独身女性が抱える寂しさを解消する8つの方法」
「60代独身男性が寂しいと感じる現実と未来を変える方法7選」
「60代で友達付き合いが面倒と感じる理由と対処法5選」